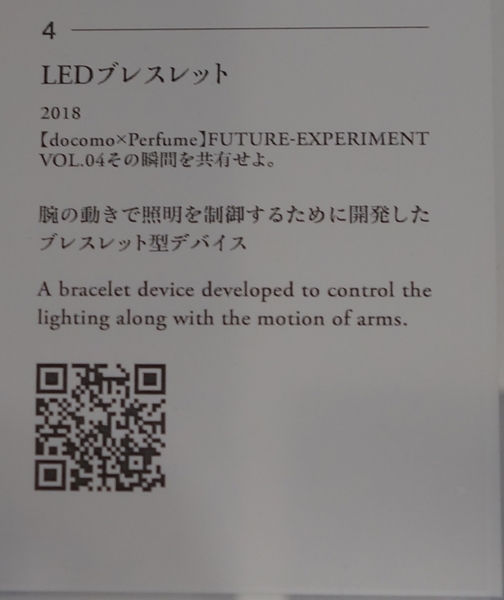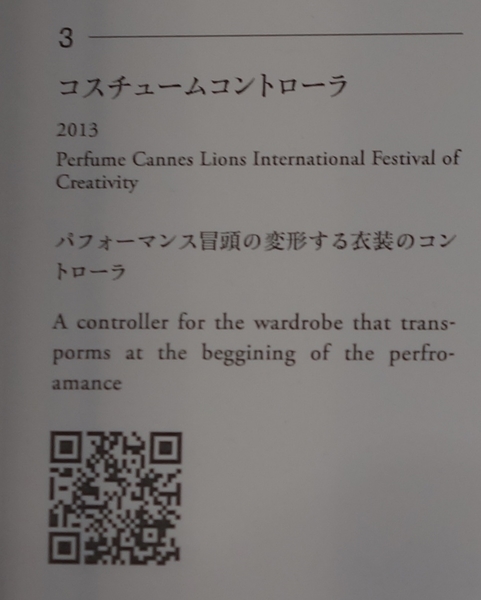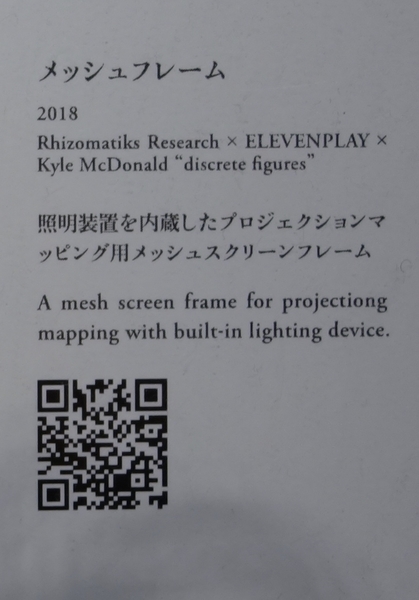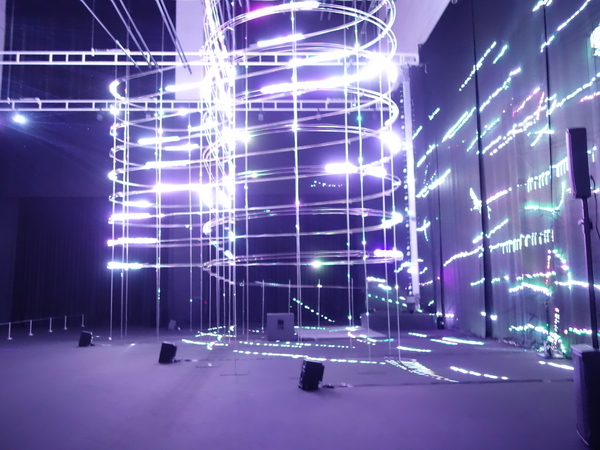翌日の4月25日からまた美術館が閉館することになった。そうとは知らず、その前日の土曜24日に「あやしい絵展」のチケットを予約していた。危うく見逃すところだった。奇しくも、この前の緊急事態宣言の発令の日は、このおなじ東京国立近代美術館にピーター・ドイグ展を見に出かけたらちょうどその日から閉館していて愕然としたのだった。美術館を閉めるのが感染拡大の抑制に効果があるのかどうかひそかに疑問。あんな無言の空間で感染する?。何かやってる演出としか思えないけどね。
それはともかく今回の展覧会でどうしても見たかったのはこの絵。

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/k/knockeye/20210425/20210425023317_original.jpg
これは秀吉に切腹を命じられた秀次の愛妾たちが四条河原で処刑される直前の様子を描いたものだそうだ。タイトルの畜生塚はまた「畜妾塚」とも書くそうだ。
画家がひとつの作品を描く場合、どこで筆を止めるかは重要で、たとえば、ダ・ヴィンチの《アンギアーリの戦い》は、どれだけ賞賛されたとしても、結局、未完にしか見えないが、この絵はこれで完成に見えるがどう?。成立の過程を知らないので、もしかしたら未完なのかもしれないが、この絵はここで筆を擱いたからこその迫力がある。もし、裸婦画としても着衣画としても完成していたら嘘くさかったろう。
甲斐庄楠音の作品群の前がいちばん人だかりしていた。




この甲斐庄楠音、速水御舟の《京の舞妓》、稲垣仲静の《太夫》など、この時期に日本画の女性像は新たな表現を手にしつつあった。しかし、稲垣仲静、速水御舟は早く死んだし、甲斐庄楠音は、土田麦僊に「穢い絵」と批判されて映画美術に転向していく。溝口健二『雨月物語』の衣装は甲斐庄楠音がデザインした。が、日本画にとっては大きな損失だった気がする。